イノベーションは「良いアイデア」ではなく、既存の合理性を一度疑い、組織の慣性を乗り越えて、学びを資産化する一連のマネジメントです。本稿では、講義で得た示唆を、実務でそのまま使える骨格に再構成します。キーワードは①組織の文脈と慣性、②ビジネスモデルの四要素、③イノベーション・ピラミッド、④両利きの経営、⑤トライ&エラー&ラーンの制度化です。
1. 「忘却が難しい」本質──文脈と慣性の解剖
変革の第一歩は、企業に堆積した文脈(歴史・制度・価値観)と、そこから生まれた慣性(癖)を徹底的に読み解くことです。多くの組織で新規事業が進まないのは、担当者の熱量不足ではなく、これまで“正しかった合理性”が強固な仕組みとして残っているからです。
- 縦割り・サイロ化は非合理の産物ではなく、既存事業で効率を最大化した当然の帰結。
- 指標・評価・人事・予算のループが既存KPIに最適化され、新規の芽を“良識的に”摘み取る。
だからこそ、変革は「現場の努力」に還元せず、仕組みを変えるゲームとして設計する必要があります。
2. 相反のダイヤルを回す──創造性×規律/スケール×フォーカス
イノベーションは矛盾の同居です。創造性と規律、スケールとフォーカス、プロセス重視と成果重視、一貫性と柔軟性。これらを二者択一で捉えず、状況に応じてダイヤルを回す前提で設計します。トップのコミットメントは、「どのダイヤルを、いつ、どこまで回すか」を明文化し、評価・資金・体制に落とし切ることにあります。
3. ビジネスモデルの四要素──因果構造で語る
ビジネスモデルは以下の四要素の一筆書きです。
- CVP(Customer Value Proposition):誰のどのジョブを、何として解決するか。ノックアウトファクター(満たせなければ失格の条件)を必ず先に特定します。
- 利益モデル:どこで稼ぎ、どこにコストが乗るか。単価・回数・継続・補助線(補助金・広告・補助収益)を明示。
- プロセス:価値を届ける反復手順。学習ループ(仮説→実験→学習→改善)をプロセスそのものに埋め込みます。
- 経営資源:人・データ・知財・ブランド・ネットワーク。借りる/買う/育てるの優先順位を明確に。
商流図だけでは“流れ”しか見えません。四要素がCVPを頂点に因果で結ばれているかで、As-is→To-beを描き、KPI・資金計画・組織設計へ接続します。
4. イノベーション・ピラミッド──変革のレイヤーを言語化
「変革」の解像度を上げるため、取り組みをレイヤーで整理します。
- レベル1:オペレーション(改善)──品質・コスト・リードタイムの最適化。
- レベル2:製品・サービス──機能・UXの刷新。
- レベル3:ビジネスモデル──収益の取り方・チャネル・エコシステムの組み直し。
- レベル4:マネジメント・イノベーション──評価・予算・組織形態など、上位のルールを更新。
自社の「変革」はどの層を狙うのかを最初に決め、学習の単位・検証サイクル・投資判断を層に合わせて設計します。
5. 「忘却装置」をトップダウンで仕掛ける
既存の合理性を上書きするには、忘却を促す制度的な装置が必要です。
- 組織分化:新規は別KPI・別評価・別稟議。
- 人事のシンボル:新規にエースを張る、既存に“飴と鞭”。
- 資金の封印:新規用のリングフェンス予算。
- 指標の切替:成果ではなく学習速度・仮説の更新率を主要KPIに。
- 儀式:外部発表や顧客コミットで退路を断つ。
「やる気の問題」にしないことが、最初の勝ち筋です。
6. CVPの解像度を上げる──ジョブ×ノックアウトファクター
CVPは抽象的なスローガンではなく、ジョブ(顧客が片づけたい用事)から逆算した仕様です。
- 顧客観察→ジョブ仮説→ノックアウトファクター(法規・互換・性能・価格)確認→CVP設計。
- 経営トップは曖昧な掛け声で混乱を広げない。具体事例を持ち寄る対話を定例化し、現場の言語で定義を更新します。
- 顧客維持は、顧客と企業が互いに学ぶ学習関係の設計。フィードバックを返し、次のジョブを共創します。
7. 変革マップ──As-is→To-beと「難所」の可視化
両利き経営の全体像は、変革マップとして見える化します。
- 軸1:四要素(CVP/利益モデル/プロセス/資源)。
- 軸2:レイヤー(オペレーション~マネジメント)。
- 軸3:時間(As-is/成り行き/To-be)。
- 付帯:難所リスト(汽水域、借用と忘却のトレード、評価制度の不整合、資源の引き剝がし、短期業績圧力)。
最初に難所を“正々堂々と”共有し、合意のルール(どの指標が優先か/誰が最終決定者か)を決めておくと、摩擦のエネルギーを前進に変えられます。
8. 分化か統合か──借用と忘却のトレード
既存と新規をどう組み合わせるかは*借用(既存資産を使う)と忘却(既存ルールを外す)のトレードで判断します。
- 借用が効く条件:ブランドや販路がCVPに直結、品質保証・規制対応の相乗。
- 忘却が必要な条件:価格モデル・開発サイクル・評価が根本的に異なる。
- ハイブリッド:初期は分化、スケール段階で段階的統合。
両者をつなぐバウンダリー・スパンナーを指名し、目標・言語・儀式を“通訳”させます。
9. 根回しの再定義──パワーと影響力を設計する
根回しは「事前挨拶」ではありません。パワーマップ(ポジション/パーソナル/リレーショナル)と矢印(依存関係)を描き、落とす順番を設計します。トップ→現場→ミドルの順に外堀を固める、あるいは逆順で“現場の既成事実”を作る。目的に応じて最短経路を選びます。
10. トライ&エラー&ラーン──学習を制度にする
挑戦の数ではなく学習の深さが競争力になります。
- 実験単位の定義:仮説・成功基準・停止条件(失敗の臨界点)を事前に合意。
- レポーティング:成功・失敗を形式知化し、検索可能に貯める。
- KPI:学習サイクルタイム、仮説の陳腐化速度、学習からの収益化率。
- ガバナンス:第三者を含む諮問委員会で節目ごとにゲート審査。
ゼロイチの自由度に甘えず、自律的に管理される枠を先に敷きます。
11. 競合排除と市場拡大のトレード
守りを固めすぎると市場が育ちません。あえて競合を泳がせ、標準・API・相互運用で“開かれた場”を作ると、総需要が拡大し、自社のコアへ正の外部性が返ってきます。プラットフォームを志向するなら、参入障壁は「参入しやすいがスイッチしにくい」設計が鍵です。
12. PPMの“タイミング”──今/成り行き/To-be
選択と集中はいつが勝負です。
- 成り行きPPMで、数年後のポジションを可視化。
- To-be PPMで、戦略的に置きたい姿と資源配分を宣言。
- “まだ儲かるうち”の撤退・売却は、資本調達力そのもの。指標はファイナンスだけでなく、学習の進捗も加点します。
13. イントレプレナーの資質──したたかな突破力
理屈が整う前に発生する“抵抗”を越えるのは、したたかな突破力です。
- 言葉の力:共通の“錦の御旗”と覚えやすいフレーズを繰り返す。
- 外堀戦術:プレス・顧客コミット・社外理事の活用で、退路を断つ。
- 飴と鞭:既存側の協力に報いる設計と、妨害への一線。
- 現場介入:難所ではトップ自ら“寝技”で橋をかける。
ロールモデルの行動を観察→模倣→内在化することが、最短の学習です。
14. CSVを成長戦略に埋め込む
社会的価値と経済的価値の両立は理想論ではありません。社会課題は中長期の需要そのもの。自社の強みで解ける領域を選び、CVP→利益モデル→プロセス→資源の一筆書きで設計すれば、寄付やCSRではなく稼ぎながら良くする持続的な仕組みになります。
15. まとめ──常態化のための「装置」を作る
イノベーションは、偶然を待つものでも、根性論でもありません。
- 文脈と慣性を読み解き、忘却を制度で仕掛ける。
- ビジネスモデルを四要素で語り、As-is→成り行き→To-beの地図を描く。
- イノベーション・ピラミッドで狙うレイヤーを決め、学習の単位・KPI・ゲートを整える。
- 分化と統合、借用と忘却のダイヤルを状況で回す。
- 根回し=パワー設計、トライ&エラー&ラーン=制度化。
忘却・借用・学習を日常化する“装置”を、経営のなかに実装することが、「イノベーション」をただの掛け声で終わらせないための重要なポイントであることを学びました。

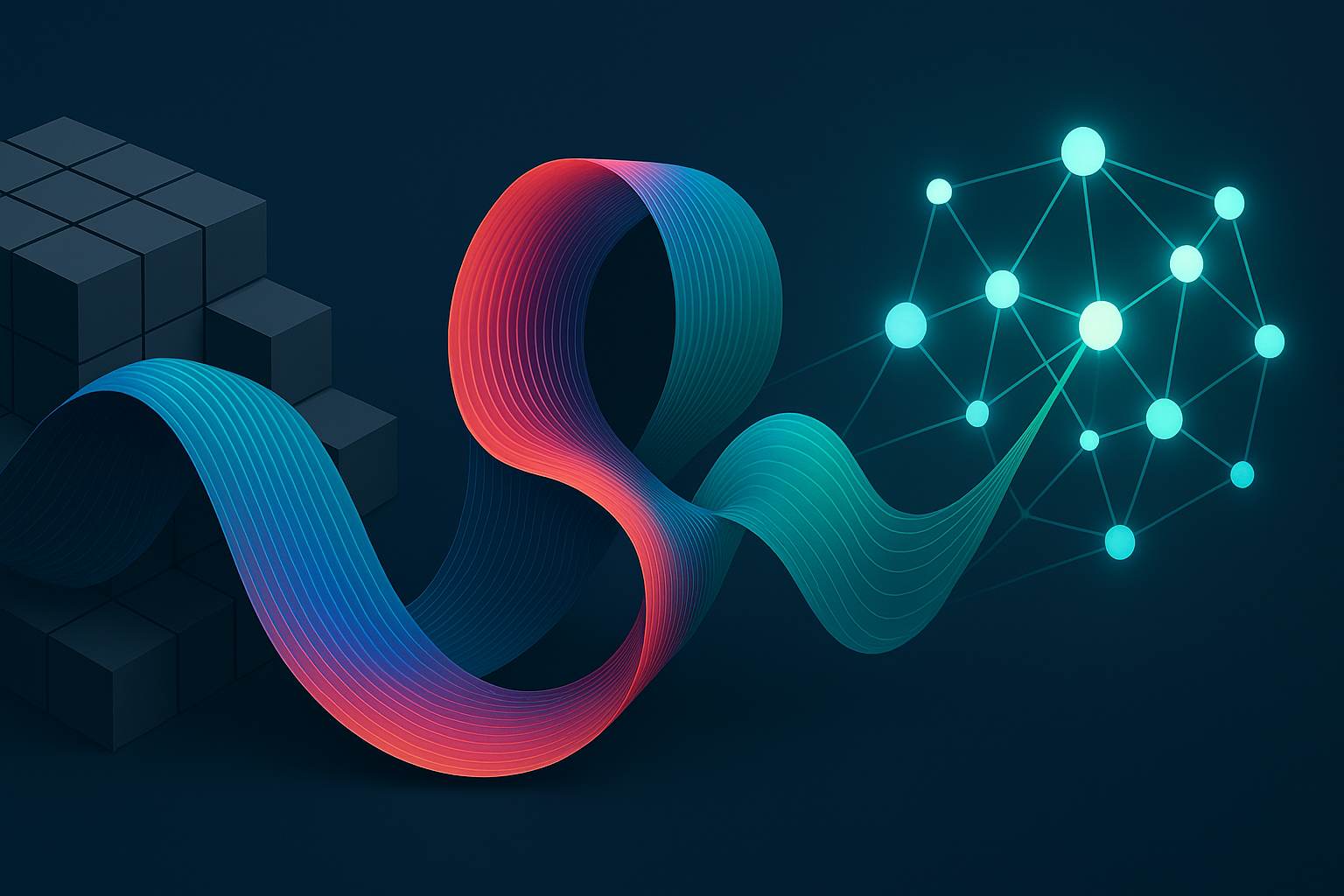








コメント