FP&A型経理を組織に定着させるための制度設計
――「経営を日常にし、AIで思考を拡張する」仕組みづくり
ここまで、経理がFP&A的視点を持ち、CFO的な感覚を養っていく流れについて見てきました。
しかし、これを個人の資質や努力に依存するだけでは、組織に定着しません。
優秀な一人が育っても、その人が辞めればまたゼロに戻る。
「できる人がたまたまいる」だけでは、会社の力にはならないのです。
今回は、FP&A型経理を組織に根付かせるために必要な制度設計の考え方、そして経営リテラシーを育てながら、AIを活用してスキルを拡張する習慣化について、掘り下げていきます。
なぜFP&A型経理は定着しにくいのか?
まず前提として、FP&A型経理は、単なる処理業務とは違い、
- 仮説を立てる力
- 経営全体を見る力
- 未来志向の対話力
など、かなり高度な視点を求めます。
一方で、中小企業にありがちな構造として、
- 数字は「過去の集計」としてしか扱われない
- 経理は「正確な記録係」として期待される
- 経営層も「レポートを受け取るだけ」で満足してしまう といった文化が根強く残っています。
つまり、期待値そのものを変えないと、個人がFP&A化しても浮いてしまうのです。
定着に必要な3つの制度設計
FP&A型経理を定着させるためには、以下の3つの制度・仕組みを整えることが鍵になります。
① ミッションを明文化する:経理部門の役割再定義
まず大前提として、経理部門のミッションを言語化し直します。
【従来型の表現】
「正確で迅速な記帳・決算を行う」
【FP&A型の表現】
「経営方針を数字と言葉で可視化し、意思決定を支援する」
ここを変えない限り、現場の意識も上がりません。
経理の役割に“経営への貢献”を正式に組み込むことが出発点です。
② 評価指標(KPI)を進化させる:処理量だけでなく提案・対話を評価する
次に、評価制度も変える必要があります。
【従来型の経理KPI例】
・月次締めのスピード
・決算の正確性
・帳簿ミスの件数
【FP&A型経理の追加KPI例】
・仮説をもとにした提案数
・経営会議での発言回数
・BIツール等による可視化提案件数
つまり、「いかに経営に働きかけたか」も正式に評価項目に加えるのです。
③ キャリアパスを設計する:経理からFP&A、そしてCFOへ
そして最後に、FP&A型経理に成長することが、
キャリアとして報われる道筋を見せることが不可欠です。
【キャリアパスの一例】
- 経理担当者(処理中心)
- ↓
- FP&Aアナリスト(分析・仮説・対話中心)
- ↓
- ファイナンスマネージャー(部門横断の財務支援)
- ↓
- CFO(経営陣の一員として未来設計)
「経営リテラシーを日常で育てる」+「AIファースト思考で能力を拡張する」
経理社員に「経営を学べ」と丸投げするのではなく、
日常業務を通じて自然に視座を上げ、AIを使いながら能力を拡張する仕組みが必要です。
具体策を整理します。
【経営リテラシーを高めるための習慣】
✅ 1ヶ月に1テーマ、経営の視点で「問い」を持たせる
例:「重点施策が粗利構造にどう影響しているか?」
✅ 数字に「ビジネス背景コメント」を1行つける
例:「販促キャンペーンが新規顧客獲得に寄与した可能性あり」
✅ 経営会議・営業ミーティングへのオブザーバー参加
現場感覚を磨き、数字の“奥行き”を捉えるセンサーを育てる
【AIファースト思考を育てるための習慣】
✅ 業務開始前に「今日はAIでどこを早く・深くできるか?」を自問する
- Excel作業、資料作成、仮説検討などでAIを活用する
✅ 「仮説づくり」にAIを使う癖をつける
- ChatGPTに売上減少時の原因パターンを仮説出ししてもらう
✅ 月1回「AI+経理実務」ミニ勉強会を開催
- 気軽にAI活用ノウハウを共有し、使い倒す文化を醸成する
AIは「思考を拡張する相棒」である
AIに仕事を奪われるかもしれないと怯える必要はありません。
むしろ、AIを使いこなす人間が、問いを持ち、仮説を語り、未来を切り拓く時代です。
経理社員がAIを自然に使い、経営の言語化と未来提案に踏み出す。
そのための「制度」と「文化」を、組織として育んでいきましょう。

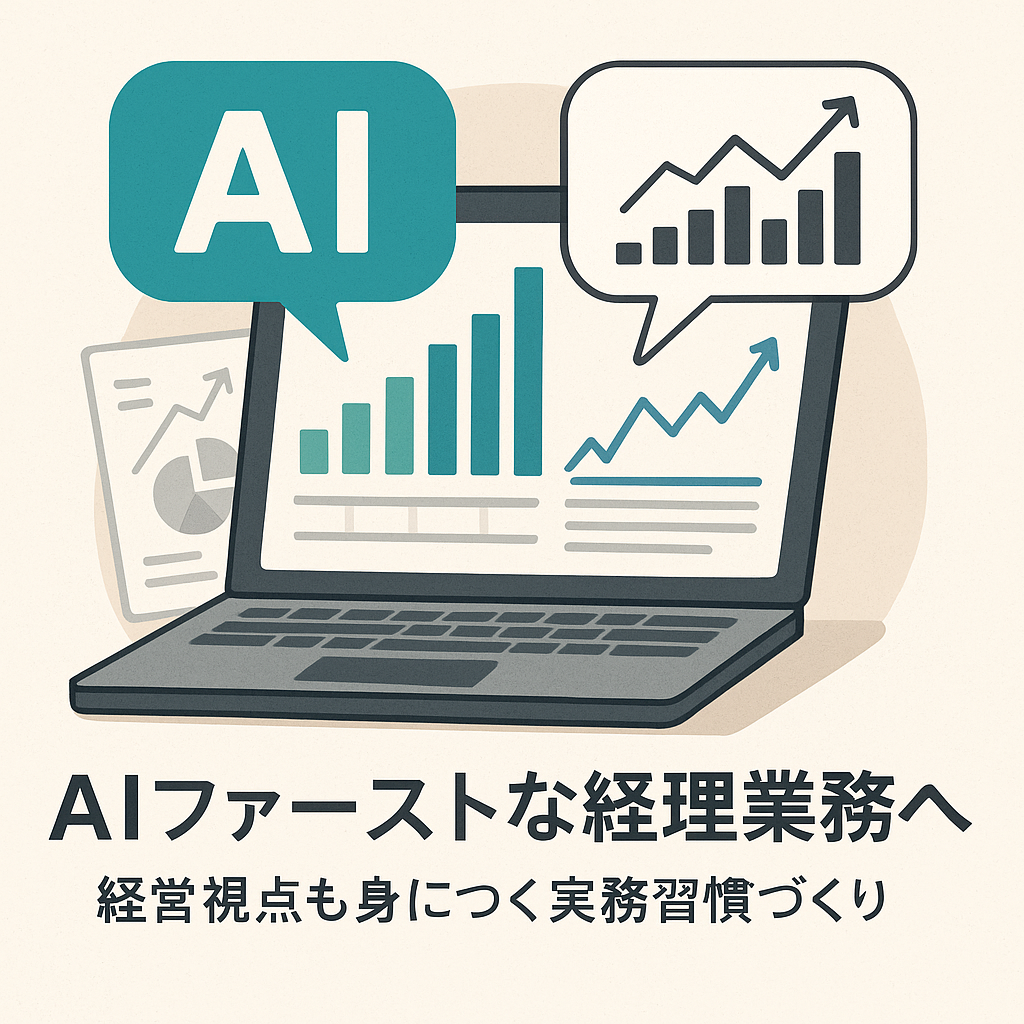








コメント