MBAでの経営戦略の学びは、私自身の思考プロセスに大きな変化をもたらしました。単にフレームワークをなぞるのではなく、問いの立て方そのものを深め、文脈を読み解き、自らの言葉で戦略を語るという経験は、実務家としての視座を一段引き上げるものでした。
本稿では、講義で得た多くの示唆から、特に実務に活かせる視点を拾い上げ、私なりの解釈で再構築してお伝えしたいと思います。
「何故の先にある何故」に迫る──問いの強さが戦略を深める
戦略立案における“問い”の持ち方の重要性を痛感しました。「なぜそうなるのか?」「他の立場から見たらどうか?」「それだけなのか?」という三つの問いを、事業構造の深掘りや因果関係の読み解きに活用することで、見落としていた視点が次々と浮かび上がってきます。
たとえば、薬局にとってのジェネリック医薬品のメリットは単なる仕入れ価格の安さだけでなく、オペレーション効率の向上による販売管理費削減にある。この気づきは、顧客(この場合は薬局)の業務構造にまで思いを巡らせて初めて得られるものでした。
一筆書きのストーリーとして語れるか?──戦略の定義の再構築
「戦略とは何か?」という問いに対し、私は今後「一筆書きのストーリーとして語れるかどうか」で判断していきたいと思います。単なるフレームワークの当てはめではなく、自社の文脈に即した因果構造を描き、それを自分の言葉で語る。
「一筆書きのストーリーとして語れるかどうか」の実務レベルでの物差しとして、私は「戦略マップとして、戦略要素の因果構造を整理したポンチエをA4で1枚に纏めきれるか」ということを掲げたいと思います。
例えば、仮に「低価格戦略」と言っても、それが成立するためには、仕入れ力・物流効率・マーチャンダイジング・販売チャネルなど、多くのファクターが構造的につながっている必要があります。これを因果関係として言語化できることこそが、戦略の本質を掴む第一歩です。
良い戦略の閾値──QCDと「非合理の理」
良い戦略を判断するための基準として、「我が社のQCD(品質・コスト・納期)はなぜ他社に真似できないのか?」という問いと、「非合理の理」が組み込まれているかどうかの二点が重要であると学びました。
特に「非合理の理」とは、合理性では説明できないが、実際には競争優位をもたらす組織の特徴や文化のこと。これは、後から意味づけられることが多いため、戦略ストーリーにおいては必ずしも意図的に組み込めるものではありません。ただ、この視点を持って企業を観察すると、戦略の再現性や模倣困難性の理解が格段に深まります。
戦略はアートとサイエンスのはざまにある
理屈で7割詰めたら、残り3割は「アート」で補う──この感覚が極めて腑に落ちました。企業とは「人の集合体」であり、最終的に戦略を動かすのもヒトです。どれだけロジカルに詰めても、最終的には「えいや!」の意思決定が必要になる場面があります。
私自身、ついファクトとロジックで完結させたくなる癖がありますが、戦略とはアートとサイエンスの狭間にあるもの。理屈で納得しつつ、最終的には胆力を持って踏み出すという姿勢が重要であると強く感じました。
資源配分の視点──PPMとオプション評価
中小企業においては、常に資源不足の前提があります。その中での経営判断は、どの事業に、どのタイミングで、どれだけの資源を投入するかという「答えのないパズル」です。
このような状況において、PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)やオプション評価のような思考フレームを使うことで、議論を可視化し、感情論から一歩離れて意思決定を行う助けになります。特に、部分最適がぶつかり合う場面では、経営者の納得感を引き出すツールとして活用できると感じています。
フレームワークの「使いどころ」を見極める
フレームワークは、問いを深めるためのレンズにすぎない。先にフレームワークありきで議論を進めてしまうと、かえって思考停止に陥るケースが多い。重要なのは、自らが立てた問いに対して、フレームワークというレンズを使って漏れをチェックしたり、抽象化して意味合いを再考したりすることです。
成功要因(KSF)の構造的・複眼的思考
KSFを語る上では、業界のコスト構造・PEST分析・顧客ニーズなどを複合的に考慮する必要があります。特定の企業戦略が業界のKSFを上書きしてしまうケースすらある──ZARAのように。成功要因とは、時に業界構造を変えるトリガーにもなる。こうした視点は戦略を再構築する際に極めて有効です。
HRMと戦略──模倣困難性の源泉
セブンイレブンやトヨタの事例のように、戦略の核心にあるのは「ヒト」の力。外から見える仕組みを真似しても、成果が再現できないのは、暗黙知に近い組織文化と能力があるからです。HRMや組織開発の取り組みが、自社戦略の模倣困難性と整合しているか?この問いを持ち続けることは、実務上も重要な示唆になります。
変化に「予測」でなく「反射」で応える
ZARAのように、高速バリューチェーンを活用し、競合の動きを反射的に捉える経営モデルに感銘を受けました。中小企業にとって同じモデルの構築は難しいですが、「創造的模倣」や「二番煎じ戦略」のようなかたちで、ニーズの兆候を素早く捉えて実行に移す反射力を持つことは、現実的な選択肢です。
バリューチェーンを部分的にいじる危険性
戦略ストーリーの整合性を保つには、バリューチェーンの各構成要素の関係性を俯瞰的に捉える必要があります。局所的な最適化が全体にどのような影響を及ぼすか。自社のストーリーにとって、何を維持し、何を変えるべきかを慎重に見極めたいと思います。
戦略の起点としてのビジョン──世界観の構築
成長戦略を描く際には、「業界の未来はどうなるか?」「その中で自社はどうありたいか?」という問いからスタートすることの重要性を学びました。「正解探し」から「問いの創出」への転換。これは、戦略家としての思考の深化に他なりません。
「強み」と「機会」は固定的ではない
SWOT分析も安易に使うべきではないと感じました。強みや機会は常に相対的で、顧客や競合の変化によってその意味が変わる。「自社の強みは何か?」という問いを、常に動的に捉える姿勢が必要です。
イノベーションのジレンマと「変化耐性」
成功の裏側には、イノベーションのジレンマという落とし穴がある。これは実務でも実感しています。環境変化に対応できる「変化耐性」をどう組み込むか──この視点は、戦略の可変性と整合性のバランスを取るために不可欠です。
経済性と戦略の関係──「差別化」の本質
差別化戦略を語る際には、「儲けの構造」から逆算する必要があります。例えばドミナント戦略の裏には密度の経済があり、それが収益性を支えている。事業経済性と戦略の整合性を見極める目を養いたいと思います。
自らを当事者に仕立てる
戦略を考える際、常に「自分が連帯保証人になれるか?」という問いを立てる。評論家的ではなく、当事者意識をもって考えることが、戦略を「生きたもの」として捉える鍵だと確信しました。
「具体⇄抽象⇄具体」の往還
安易な抽象化に走らず、固有のコンテキストを丁寧に読み解くこと。企業ごとに異なる背景を理解し、その文脈から意味を導き出す力が、戦略の再現性と納得感を高めます。
モノからコトへ、そしてエコシステムへ
製造業であっても、「モノ売り」から「コト提供」への転換は必須です。その際には、自社単独ではなく、生態系全体での付加価値創出を考える必要がある。誰と組み、どのレイヤーで戦うのか──この発想は、戦略設計に新たな視座を与えてくれました。
組織能力の「形成過程」を読み解く
VRIOなどでの静的評価だけでなく、組織能力が形成されてきた「プロセス」に着目する。社史・沿革・経営者の判断といった流れを辿ることで、企業の真の強みを理解することができます。
意図的戦略と創発的戦略のギアチェンジ
どちらか一方に固執せず、柔軟に行き来する設計が重要です。意図した戦略から始まり、創発を取り込みながら修正していく──このギアチェンジを可能にする組織設計こそが、競争優位の源泉だと思います。
戦略とは単なるロジックではなく、問いの立て方と構造理解、そして「生きた文脈」への感受性によって磨かれるものです。
MBAでの学びを通じて、私は「自分なりの戦略眼」を手に入れるための旅の入り口に立ったのだと感じています。実務の現場において、この旅を続けていくことこそが、私の実践としての経営戦略そのものであると考えています。

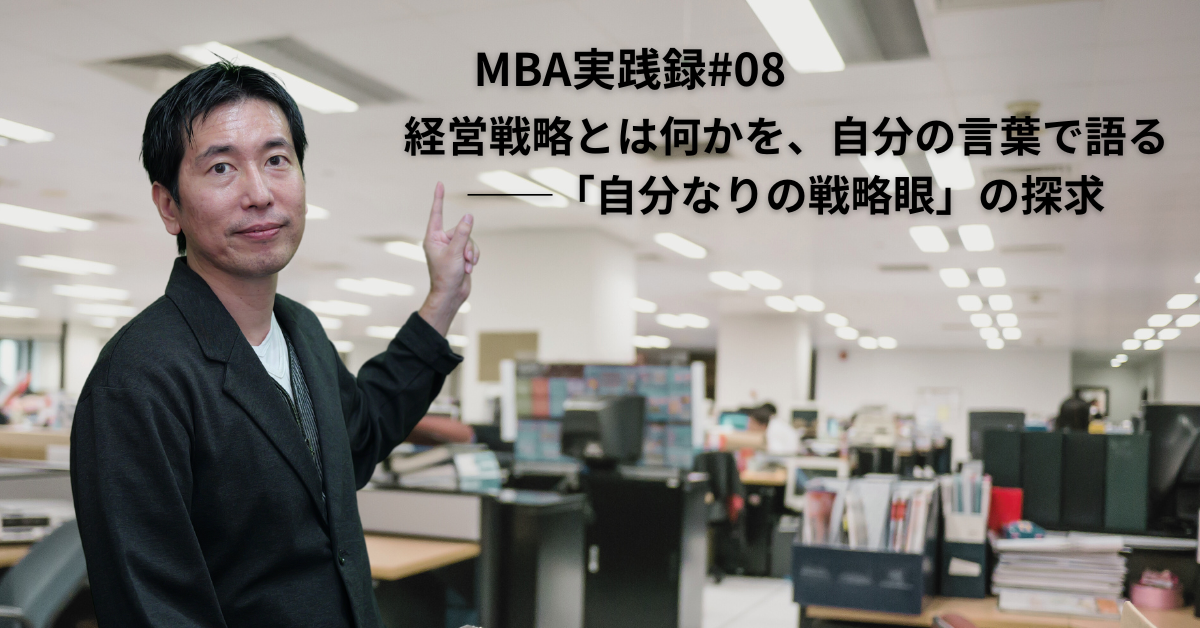








コメント