はじめに
2024年9月、日本企業の会計実務に大きな変革をもたらす新リース会計基準が公表されました。2027年4月以降に開始する事業年度から強制適用となるこの新基準は、従来の会計処理を根本的に変える可能性があります。経営者として、この変化にどう対応すべきか、今から準備を始めることが重要です。
新リース会計基準とは?基本的な概要
背景と目的
新リース会計基準は、国際会計基準(IFRS第16号)との整合性を図ることを主な目的として策定されました。これにより、日本企業の財務諸表がより国際的に比較可能になり、投資家の理解促進が期待されています。
適用時期
- 強制適用:2027年4月1日以降開始する事業年度
- 早期適用:2025年4月1日以降開始する事業年度から可能
最重要な変更点:オンバランス化の義務
従来の会計処理では、ファイナンスリース(解約不能・フルペイアウトという2つの要件を満たすリース)のみが貸借対照表に計上されていました。
しかし、新基準では:原則としてすべてのリース取引を貸借対照表に資産・負債として計上
これまで費用処理していた賃貸借取引も含め、リースの種類に関係なく「使用権資産」と「リース負債」として計上することになります。
リースの新定義と判定基準
新定義
新リース会計基準では、リースを以下のように定義しています:
「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」
この定義はIFRS第16号と整合させており、借手と貸手の両方に適用されます。
会計処理モデル
新基準では、単一の会計処理モデルを採用します:
- 使用権資産の計上
- リース負債の計上
- 使用権資産に係る減価償却費の計上
- リース負債に係る利息相当額の計上
財務諸表への具体的な影響
貸借対照表への影響
| 項目 | 変化 | 影響 |
|---|---|---|
| 総資産 | 増加 | 使用権資産の計上により大幅増加 |
| 総負債 | 増加 | リース負債の計上により大幅増加 |
| 純資産 | 変化なし | 初期認識時点では影響なし |
損益計算書への影響
| 項目 | 従来 | 新基準 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 費用科目 | 支払リース料(販管費) | 減価償却費+支払利息 | 費用の性質変更 |
| 営業利益 | – | 増加 | 支払利息が営業外費用へ移動 |
| EBITDA | – | 増加 | 減価償却前利益の増加 |
重要な財務指標への影響
悪化する指標
1. ROA(総資産利益率)
- 総資産の増加により比率が低下
- 企業の資産効率性の評価に影響
2. 自己資本比率
- 総資産・総負債の増加により比率が低下
- 財務安全性の評価に影響
3. 資産回転率
- 総資産の増加により回転率が低下
改善する指標
1. EBITDA(利払い前・税引き前・減価償却前利益)
- 支払リース料の減価償却・利息への振替により増加
- 企業価値評価で重要な指標
2. 営業利益
- 支払利息が営業外費用へ移動により増加
3. 営業キャッシュフロー
- リース料の元本部分が財務CFへ移動により増加
業種別影響度分析
高影響業種
小売業・外食業
- 多数の店舗賃貸借契約
- 総資産の大幅増加が予想
運輸業・物流業
- 車両・倉庫等のリース契約
- 設備投資の実態がより明確に
IT・通信業
- オフィス賃貸、機器リース
- 成長投資の透明性向上
中程度影響業種
製造業
- 工場・設備のリース契約
- 既存の設備投資との区別が重要
金融業
- 店舗・ATM設置場所のリース
- 規制上の自己資本比率への影響要注意
低影響業種
不動産業
- 自社保有物件中心のビジネスモデル
- テナント募集等の賃貸業務への直接影響は限定的
企業が今すぐ始めるべき5つの準備
1. 契約の網羅的な洗い出し
対象契約の例:
- 不動産賃貸借契約(オフィス、店舗、倉庫)
- 車両リース契約
- IT機器・設備リース契約
- 複合機・OA機器レンタル契約
2. 影響度の定量分析
分析項目:
- 総資産・総負債の増加額
- 財務指標への影響度
- 財務制限条項への抵触リスク
- 格付けへの影響
3. 会計方針の検討・決定
主要な選択肢:
- 少額資産の認識免除(通常は年額60万円以下)
- 短期リースの認識免除(12ヶ月以内)
- 減価償却方法の選択
- 割引率の設定方法
4. システム・業務プロセスの整備
必要な対応:
- リース契約管理システムの導入
- 会計システムの改修
- 内部統制の見直し
- 決算業務プロセスの再構築
5. ステークホルダーとのコミュニケーション
対象者:
- 投資家・アナリスト
- 金融機関(融資条件の見直し)
- 監査人
- 社内関係部署
中小企業への影響と対応策
適用対象の考慮事項
新リース会計基準は、上場企業および会計監査人設置会社が主な適用対象となります。多くの中小企業では直接的な影響は限定的ですが、以下の場合は検討が必要です:
- IPO準備企業
- 大企業の子会社
- 金融機関からの要請がある企業
中小企業の準備ポイント
- 現状把握: リース契約の規模・重要性の評価
- 簡便的処理の活用: 少額・短期リースの免除規定の活用
- システム投資の最適化: 規模に応じた現実的なソリューション選択
実務担当者向けスケジュール
2025年中に完了すべき事項
- [ ] 現状分析・影響度評価
- [ ] 会計方針の仮決定
- [ ] システム要件の整理
- [ ] 内部統制設計の検討
2026年中に完了すべき事項
- [ ] システム導入・テスト運用
- [ ] 会計方針の最終決定
- [ ] 社内研修・教育
- [ ] 監査人との事前協議
2027年3月までに完了すべき事項
- [ ] 本格運用開始
- [ ] 開示資料の準備
- [ ] ステークホルダーへの説明
よくある質問と回答
Q1: すべての賃貸借契約がリース会計の対象になるのですか?
A1: いいえ。新基準では「原資産を使用する権利の移転」という定義に基づき判定されます。単純なサービス契約は対象外です。
Q2: 財務制限条項に抵触するリスクはどう対処すべきですか?
A2: 事前に金融機関と協議し、新基準適用による財務数値の変動を織り込んだ条項への見直しを検討することが重要です。
Q3: システム導入にはどの程度の費用がかかりますか?
A3: 企業規模や契約数により大きく異なりますが、中規模企業で数百万円から数千万円程度が一般的です。各種システムベンダーとの早期相談をお勧めします。
まとめ:経営者が今取るべきアクション
新リース会計基準の導入は、単なる会計処理の変更ではなく、企業の財務戦略そのものに影響を与える重要な変革です。
今すぐ始めるべき3つのアクション:
- 現状把握: 自社のリース契約の棚卸しと影響度分析
- 体制整備: プロジェクトチームの組成と責任者の明確化
- 外部支援: 会計士・システムベンダーとの連携体制構築
2027年4月の強制適用まで残り約2年。早期の準備開始により、新基準を企業の競争力向上につなげることが可能です。
参考資料:
関連記事:

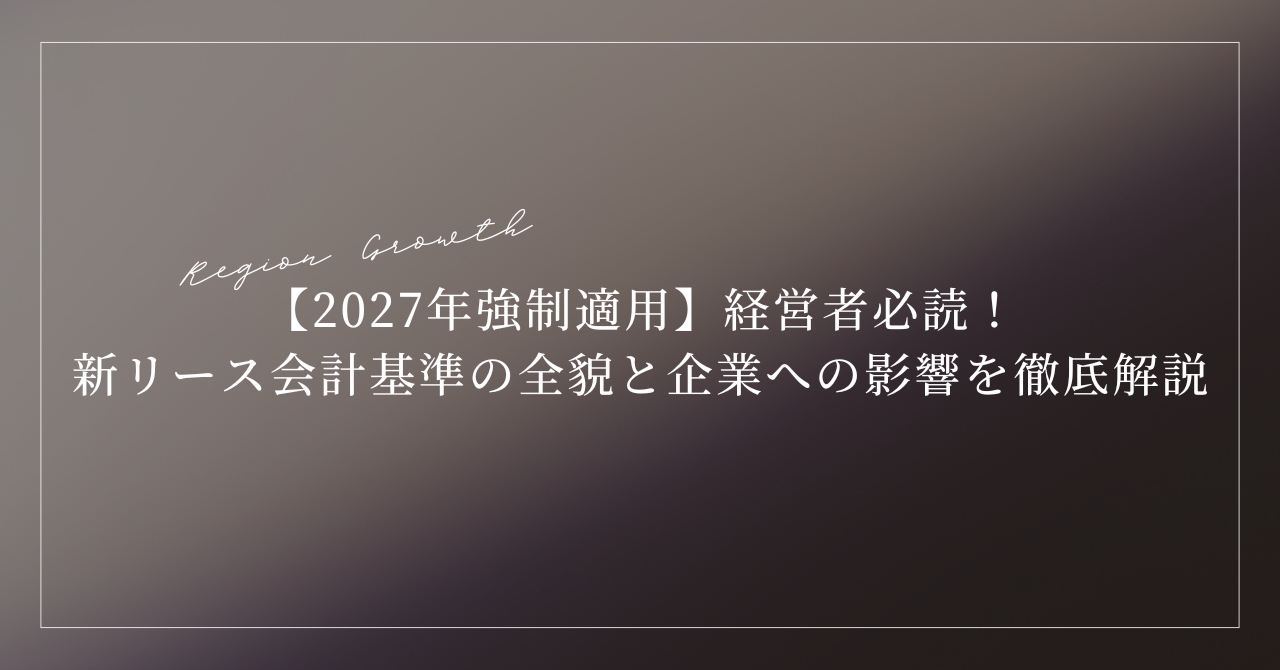








コメント