「財務戦略」という言葉はよく耳にするのに、「会計戦略」「税務戦略」といった表現は、あまり一般的ではないかもしれません。
しかし、企業が持続的に成長するためには、財務だけでなく、会計と税務も“戦略”として位置づける視点が不可欠です。特に中小企業においては、限られた資源を最大限に活かすためにも、会計・税務を“受け身”ではなく“攻め”の道具として使うことが、経営の質を大きく左右します。
会計・税務は「記録」ではなく「設計」の領域へ
従来、中小企業にとっての会計や税務は、「記録」と「申告」が主たる目的と捉えられがちでした。
つまり、「いくら儲けたか」「いくら納税するか」といった過去の結果の整理にとどまり、戦略的な位置づけがなされにくい領域だったと言えます。
しかし、事業環境の複雑化や資金調達の多様化、さらには事業承継やM&Aといった重要な意思決定が増える中で、会計と税務は“経営設計”のための重要なレイヤーとなりつつあります。
「会計が経営をつくる」と言っても過言ではありません。
例えば、会計方針ひとつで、利益の出方、BS(貸借対照表)の見え方、キャッシュフローの流れは大きく変わります。
その結果、銀行の評価、投資家や買収先からの評価、果ては従業員の納得感までもが左右されます。
制度変更にみる“会計の重み”──のれん・リース会計の見直し
2025年以降、上場企業ではいくつかの重要な会計制度変更が控えています。代表的なものに「のれんの非償却論」や、「リース会計基準の見直し」があります。
たとえば「のれん」は、企業が他社を買収した際に発生する“目に見えない資産”であり、現在の日本基準では償却が義務づけられていますが、国際的には非償却・減損のみが主流です。この扱いの差が、買収意欲や企業価値評価、財務の見せ方に大きな影響を与えています。
また、リース会計基準が見直され、オペレーティング・リースもBS計上の対象となる方向で議論が進んでいます。これは、企業の「見せ方」を大きく変える制度変更です。
一見すると上場企業特有の話題のように見えますが、実は中小企業経営にも深い示唆を与えます。
中小企業こそ「経営目的から逆算した会計」が必要な理由
制度変更に対して、上場企業は会計方針を再構築し、経営戦略にフィードバックをかけています。それは「見せ方=経営資源」であることを理解しているからです。
同様に、中小企業においても、「どんな経営をしたいか」から逆算して、会計方針や税務戦略を設計することが、経営を飛躍させる大きな鍵になります。
たとえば、将来的にM&Aによる事業拡大を視野に入れている企業であれば、会計方針による利益の安定性やBSの健全性が、企業価値評価に直結します。
事業承継を控えている企業であれば、株価評価のための資本政策と密接に絡む形で、税務の繊細な設計が求められます。
また、資金調達の場面でも、銀行や信用保証協会が重視するのは「税務申告書」だけではなく、「会計上の健全性」「将来予測の妥当性」など、会計戦略的な観点が問われるケースが増えています。
実践例:会計・税務戦略で変わる経営の風景
以下のような実例は、会計・税務を戦略的に位置づけた中小企業の成功事例です。
- A社(製造業):原価計算の見直しによって、実際には収益性の高い製品群に注力できるようになり、粗利率が10%改善。
- B社(サービス業):M&Aに備えて3年前から利益の平準化と資産の整備を実施。結果として買収時に1.5倍の企業価値評価を獲得。
- C社(小売業):リース契約の見直しにより、将来的な負債圧縮の道筋をつけ、銀行からの借入枠を拡大。
いずれも「専門家任せ」ではなく、経営者自身が経営戦略と会計・税務の接続点を理解し、意思を持って判断した結果です。
「意思決定に会計の声を入れる」経営へ
会計や税務は、確かに専門性が高く、外部の会計士・税理士に任せる部分が多くなる領域です。しかし、それは“手続き”の部分。
本来、経営者が握っていなければならないのは、「どんな未来を設計するか」という意思の部分です。
会計戦略・税務戦略は、単なる数字の調整ではなく、会社のビジョンを数字に落とし込む「経営言語」でもあります。
記録するための会計から、未来を創るための会計へ。
「納税のための税務」から、「企業価値を守るための税務」へ。
こうした視点を持つことで、会計・税務は経営にとっての“強い武器”となります。

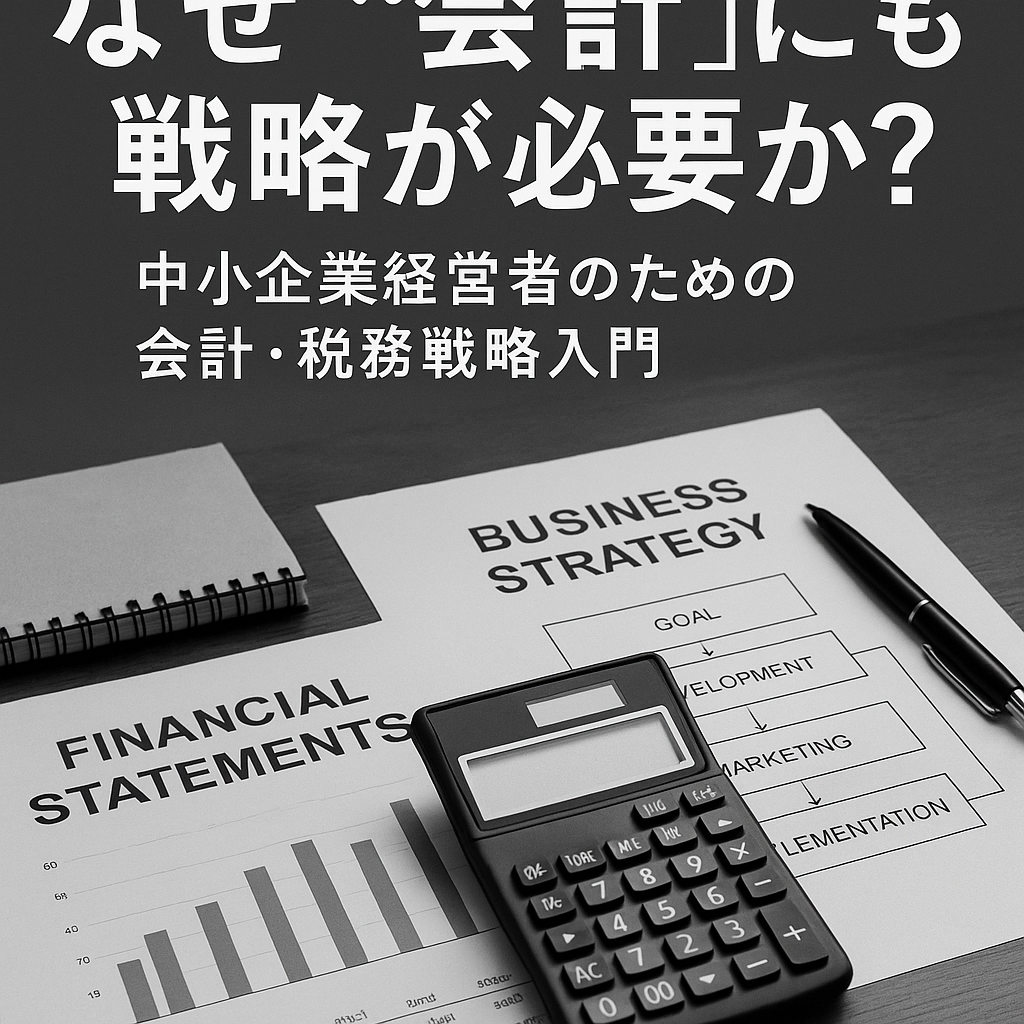








コメント